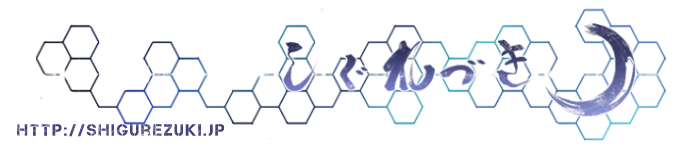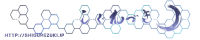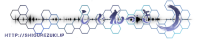概要
小烏丸(こがらすまる)とは、現存する日本刀の中で最も古い時代の物の一つで、平家一門の家宝でったと伝えられている、刀工「天国」(あまくに)作と伝えられる日本刀である。
刀身・外装
刃長62.7cm、反り1.3cm、腰元から茎にかけ強く反っているが、上半身に反りは殆ど無い。
表裏に太目の樋を、棟方に掻き流しの薙刀樋を掻く。
鍋は通常の日本刀のとは異なり、刀身のほぼ中央にある。
刀身の先端より半分以上が両刃となっており、日本刀としては独特の刀身をしている。
この形状のことを鋒両刃造(きっさきもろはづくり、ほうりょうじんづくり)と呼び、以降は鋒両刃造の事を総称して「小烏造」と呼ぶようになった。
一般的な日本刀との差
通常の日本刀同様に反りは存在するが、刀身の半分以上が両刃になっていることから、断ち斬ることに適さず、刺突に適した形状となっている。
伝承・伝来
桓武天皇の時代に、伊勢神宮より遣わされた八尺余りある大鴉「八咫烏」が空より舞い降りてきて、その羽から出てきたという伝承が存在する。
「小烏丸」という名はこの伝承に由来している。
後に平貞盛が平将門、藤原純友らを反乱鎮圧する際に天皇より拝領し、以後平家一門の家宝となる。
その後、壇ノ浦の合戦後行方不明となったとされたが、天明5年(1785年)に、平氏一門の流れを汲む伊勢家で保管されていることが判明し、伊勢家より刀身及び刀装と伝来を示す「伊勢貞丈家蔵小烏丸太刀図」の文書が幕府に提出された。
一度は伊勢家により徳川将軍家に献上されたものの、将軍家はそのまま伊勢家に預け、明治維新後に伊勢家より対馬の宗家に買い取られた後、明治15年(1882年)に宗家当主の宗重正伯爵より明治天皇に献上された。
現在はこれが皇室御物「小烏丸」として、外装ともに宮内庁委託品として国立文化財機構で保管されている。
なお、刀工「天国」作という説があるが、現存するものは生ぶ茎、すなわち無銘である。
関連項目
コメント
- コメントはまだありません。