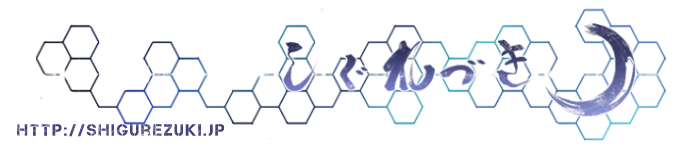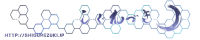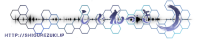概要
未編集
神社の起源
神社のことをよく「お宮」「お社」と呼ぶ。
社(やしろ)というのは屋(や)と代(しろ)の義である。これは神々が住まう家の代わりを意味したのではないだろうか。
本来、神社には社殿がなかったと聞く。そこが神域であれば岩や石、あるいは柱、しめ縄で囲った結界でもなにか神聖であることを示す目印があればよかったのである。
なぜなら、神々は祭りの時だけ天上より降臨し、祭りが終わった後は天上へと帰っていくと信じられていたからだ。
しかし、神々が降臨するには依代が必要となる。これを神籬(ひもろぎ)や磐座(いわくら)としたのだ。
つまりは、神社とは本来、神事を行うことの出来る空間と神々が降臨する目印さえあれば、そこは神社と呼べる場所となる。
神社と森
神社の木立のことを「杜」という。(詳しくは杜を参照)
杜とは土を主としたもので、森とは木を主としたものであるが、「鎮守の森」「鎮守の杜」などの言葉があるようにどちらも同義語とされ、神が斎き坐しまし、あるいは神々が降臨するところがモリなのだ。
東京などの都市等にある神社を見ると神社の周りには必ずと言っていいほど木々が生えて、大小の森が存在しているのがわかる。
このように神社と森は切っても切れない関係にあるのだ。
参拝
神社への参拝には主に"一般"と"正式"の二通りがある。
いずれも願いがかなったら再度お礼の参拝をしたほうが良い。
一般参拝
別名「社頭参拝」とも言う。この一般参拝の代表としては初詣などがある。
正式参拝
別名「昇殿参拝」とも言う。これは初穂料を納めて祈祷をお願いし、拝殿に上がってから参拝するところから着ている。祝詞の奏上などが行われる。代表としては七五三や厄年などがある。
関連項目
コメント
- コメントはまだありません。