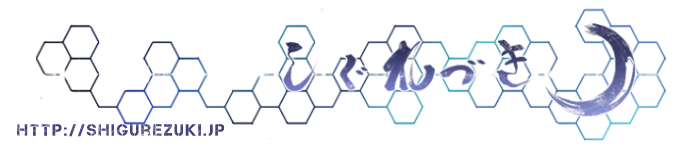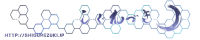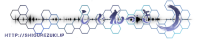概要
月の軌道は正円ではなく楕円で、公転と同じ周期で自転もしているため地球に対して常に同じ面を向けいる。
地球側の面を月の表、反対側を月の裏と呼び、内部構造はマントルと核の地球と極めて同様と考えられている。しかし、マントル対流ではなく死んだ状態である。
ちなみに月には大気がなく真空とされているが、正確にはナトリウムやカリウムなどの希薄なガスがあり、大気の定義には当てはまっている。しかし非常に希薄なためほとんど真空と呼んでも差し支えないほどである。
月が輝く理由
月の表面にレゴリスと呼ばれる隕石の衝突や火山の噴火によって溶けたガラスや溶結土からなる、直径10~1000マイクロメートルの細かい粒子が太陽光線を反射しているから。
月の物質
陸の部分はカルシウムやアルミニウムから成る斜長石を多く含む斜長岩(アノーソサイト)でできている。
海の部分は玄武岩でできている。ちなみに月の海と呼ばれるのはこの玄武岩の部分のことである。
月の起源
現在もまだ明確なところは分かっていないが4つの説が挙げられている。
分裂説(親子説・出産説)
地球の自転により一部が分裂し月となったとする説。
たしかに月の物質が地球のマントル物質に似ているが、地球から月が分裂するには相当な遠心力が必要であり、それほどの遠心力が生まれるほど地球の自転速度が速かったとは考えにくい。
捕獲説(他人説・配偶者説)
別の場所で生まれた天体がたまたま地球のそばを通過する際に地球の重力の捕らわれてそのまま衛星となったとする説。
しかし天体が別の天体の重力に捕まって衛星となる確率は天文学的数字と言えるほど低く、地球と月の物質が類似していることの説明にはならない。
共成長説(兄弟説・双子集積説)
地球の誕生とほぼ同じことに、同じガス塊から月も誕生したとする説。
地球の月の平均密度の違いや月の組成が地球内部のマントル物質に似ているのかという謎の説明にはならない。また、同時に形成されたとすると、現在の観測から予想されている月の核のサイズは小さすぎるという指摘もある。
ジャイアント・インパクト説(巨大衝突説)
約46億年前、地球の形ができてまだ間もないころに地球の半分ほどの大きさの原始惑星が衝突し、原始惑星は砕け散り宇宙空間に撒き散らし、同時に地球のマントル物質の一部を放出した。
破片の一部は地球に落下したが、多くの破片が地球の周回軌道に残り、やがて破片同士がぶつかり合いくっつき合って月が形成されたという説。
現在の状況からこの説が有力な説とされている。
月の歴史
マグマオーシャン説
約45億年前、当初月の表面はどろどろに溶けた熱いマグマの海が存在していたと考えられる。
マグマよりも密度の低い斜長石が浮かび上がり、それが斜長岩として厚さ200キロメートルほど固まったとされる。
その後内側の部分が玄武岩として固まったと考えられる。
共通重心
月は地球を楕円状に回ってると前述したが正確には共通重心と呼ばれる重心があり、これは月が地球の周りを回っているのと同時に、小規模ではあるが地球も月の周りを回っていることになる。
例えば重い鞄などを手にとって回ってみると自分を中心に鞄が回っているように思うが、実際は自分も少し鞄に振り回され小さな円を描いてる、なんてことはないだろうか。
つまりはそういうことだ。
ちなみに共通重心は以下の計算から簡単に割り出すことが可能である。
(月-地球間の距離)×(月の質量)÷(地球の質量)=共通重心
結果、共通重心は地球の重心から約4600キロメートル離れた場所にあることがわかる。
月震
いわゆる月で起こる地震のこと。
深発月震
深さ800~1100キロメートルの地点で発生する。規模はM(マグニチュード)1~2程度。周期的に発生することが多く、そのため月と地球の引力が関係している可能性が考えられている。
浅発月震
深さ300キロメートルの地点で発生する。規模はM3~4程度。頻度が少なく発生原因も不明。
隕石の衝突
月に設置された地震計には隕石の衝突による月震も観測されている。
熱月震
月面の岩が昼夜の寒暖差に耐えられず崩壊した際に起こる。規模は非常に小さい。
人工月震
役割を終えた探査機が月面に落下することで発生。
なお、地震系が設置されたのは表だけなので裏の状況はまだ分かっていない。
衛星としての月
月が衛星というのはいまさら言うまでもないが、では衛星の大きさや惑星と衛星の比率などは考えたことがあるだろうか。
月の大きさは同じ衛星であるガニメデ、タイタン、カリスト、イオに続いて5番目に大きい。
ちなみに2006年に準惑星にされた冥王星はこれらの比じゃないほど小さい。
比率に関しては土星の衛星タイタンの場合、直径が約1/20、質量比が約1/47000に対して、地球の衛星月は直径が約1/4、質量比が約1/81であり、衛星としてはかなりの規模であることがわかる。
上記の事から地球に対して不釣合な大きさから二重惑星だという意見もある。
しかし前述のように共通重心が地球内部にある地球と月に関しては二重惑星とは言えないが、太陽系内においては稀有な関係ではある。
月に水の可能性
現在、月の永久影と呼ばれる月の南北極地付近のクレーター内部でクレーターの壁が太陽光を遮り永久に太陽の光が当たらない場所に氷が存在しているのではないかとされている。
1994年にNASAの月探査機「クレメンタイン」によるレーダー観測で月の南極を中心とする緯度2・5の範囲で特異な観測データが得られた。
1998年にはNASAの探査機「ルナー・プロスペクター」によって、中性子分光器による観測された結果、極地に水素が凝縮していることが確認された。
しかし、日本の月周回衛星「かぐや」による永久影の観測では表面に氷が存在を示す証拠は得られなかった。
2009年、NASAの月面衝突用探査衛星「エルクロス」によって月面衝突時に飛散したチリの観測データを分析した結果、水蒸気を観測。
その翌年2010年にはNASAがインドの月探査機「チャンドラヤーン1号」に搭載した開口レーダーによって、北極付近の比較的小さなクレーターの永久影に少なくとも6億トンほどの氷を発見した。
関連項目
コメント
- コメントはまだありません。